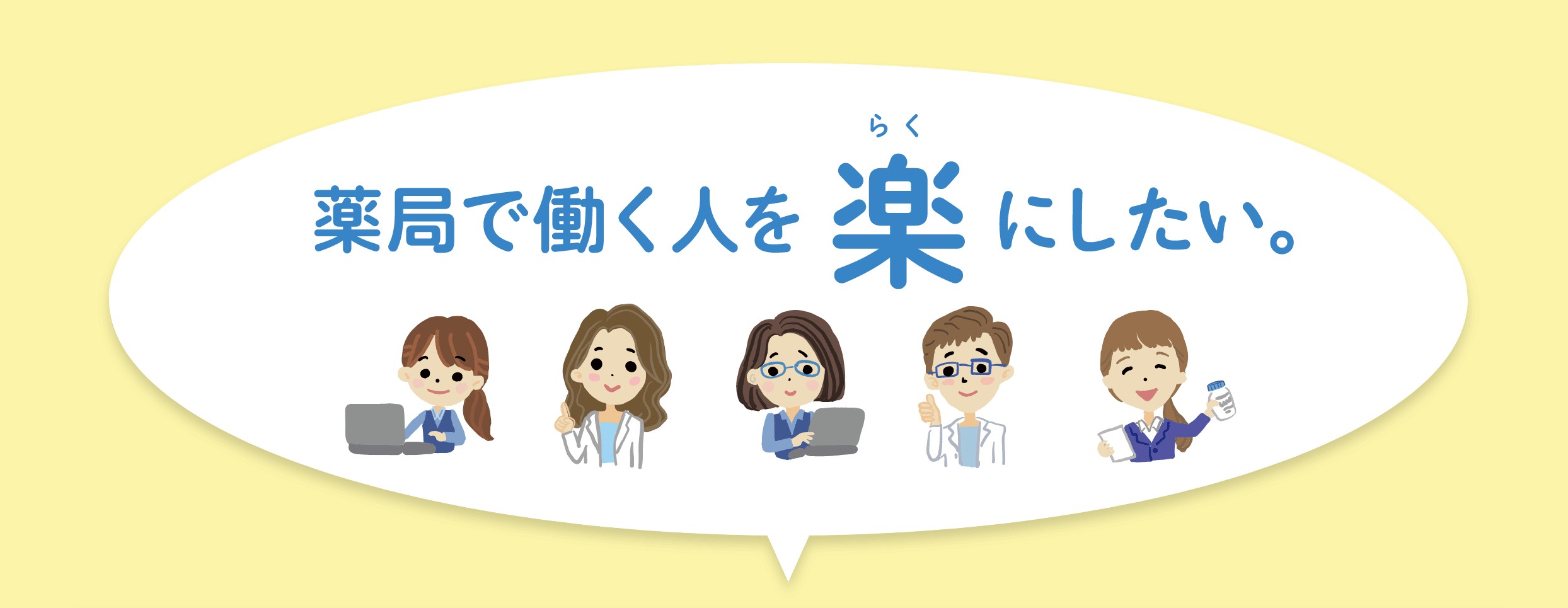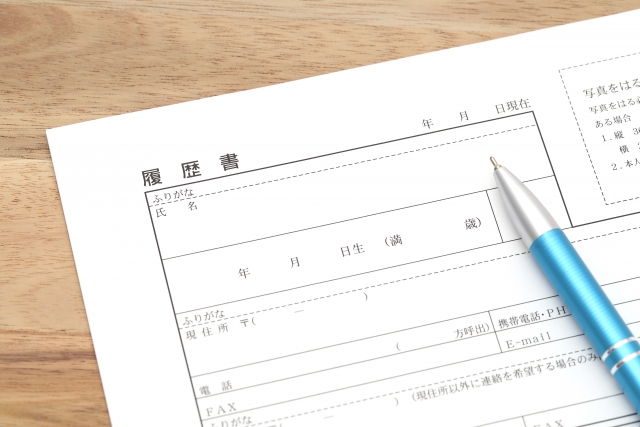1. はじめに:何かとよく聞く「薬歴AI」
近年、「AI」という言葉を耳にする機会が非常に増えました。寝ても覚めてもニュースなどで話題が尽きませんよね。特に、さも人間とチャットをしているかのような返事をしてくれる「生成AI」は一世を風靡し、今もなお話題です。この生成AIを使った「薬歴AI」なるものが昨今どんどん出てきているわけですが、結局のところこれは何なのでしょうか?薬剤師として長年勤務を行い、また、薬歴音声入力AI「Kakeru君」の開発企画に携わらせていただいたメンバーの一人として、僭越ながら私見を述べてみます。
2.「薬歴」周辺キーワードの整理
2.1. 薬剤師にとっての「薬歴」
薬剤師の皆様にとって、日々の業務で欠かせないのが「薬歴」の作成です。しかし煩雑な作業に時間を取られ、やむを得ず薬歴作成のための残業が発生してしまうこともあるのではないでしょうか。負荷が多くなりがちな薬歴作成においてAIが支援できれば、薬剤師の業務効率は飛躍的に向上します。現在、多くの企業がこの「あったらいいな」を実現するため、新機能の開発に力を入れています。とはいえ、薬歴は薬局や薬剤師ごとに独自の形式や表現方法が色濃く反映されるため、AIがその構造を理解し、適切な薬歴を作成するのは容易ではありません。この解釈こそが、各社の技術力の差となる「秘伝のタレ」と言えるでしょう。

2.2. 「生成AI」とは?
AIと言っても様々なものがありますが、Kakeru君にも使用されているのは、著しい進化を遂げている「生成AI」です。生成AIとは、既に学習したデータをもとにテキストや画像などの新しいコンテンツを生成する人工知能のことを指します。生成AIは、まるで「とても素直で物分かりの良い小学生」のように、指示された内容を理解し、実行することに長けています。しかし、専門的な知識や思考プロセスを自ら持っているわけではありません。そのため、実際の業務がどのような手順で進められているのかを細かく定義する必要があります。また生成AIは、あたかも事実かのように存在しない情報を生成してしまうことがあるため、その特性を理解し、適切に制御することが重要です。
3. 薬歴音声入力AI「Kakeru君」とは?
3.1. Kakeru君 開発秘話
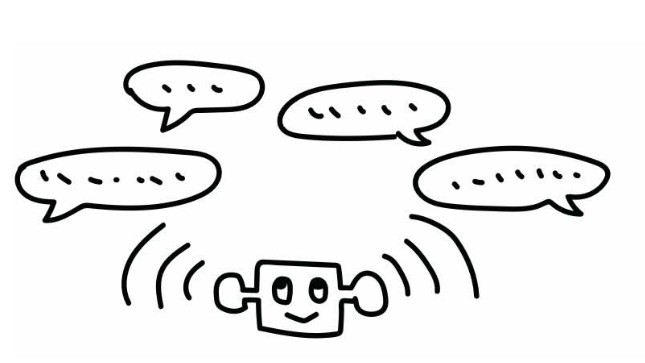
Kakeru君の開発は、mediLab代表の一言から始まりました。初期の名称は「薬歴一緒に準備丸(仮)」というものでした。ダサいですね笑。社内ではやんわりと各メンバーが名前を変えるように代表を促し、結果として薬歴音声入力AI 「Kakeru君」というネーミングに決まりました(僭越ながら Kakeru君 は私起案です。ちょっとだけ誇らしいかもしれません)。
ネーミング決定と並行し、優秀なエンジニアが集結したmediLabでは、わずか1週間で操作画面のプロトタイプが完成しました。名前より先にプロトタイプがあった形です。その時から「Kakeru君」は、薬剤師の服薬指導中の会話を録音し、文字起こし、要約、そして指定された形式での薬歴作成を簡単な操作で実現しておりました。しかし薬歴は薬剤師ごとに形式や表現方法が大きく異なるため、まずは「mediLab流」の薬歴を定義するために複数の薬剤師にインタビューを行い、薬歴に記載する内容や形式を整理することから始めました。またAIが事実に基づかない情報を生成しないように、様々な工夫を凝らしました。初期の頃は、音声認識精度が低く、会話内容を誤って解釈し、想定外の薬歴が作成されてしまうこともありました。幾多の課題を乗り越え、実用的な時間で薬歴を出力できるよう調整を重ね、薬局業務に精通したエンジニアによる細やかなチューニングを経て現在の形に至りました。
3.2. Kakeru君の機能
Kakeru君の最大の特徴は、高い音声認識精度と薬剤師の意図まで汲んだSOAP案の執筆機能です。既存の薬歴システムに依存せず、シンプルな機器構成で動作することも大きなメリットです。また、現役の薬剤師によるテストとフィードバックを重ねることで、常に進化を続けています。音声認識・SOAP案作成の機能の基礎品質はもちろんのこと、さらなる機能をweeklyなペースで更新・リリースし続けています。
3.3. mediLabの得意分野
私たちmediLabは、「最先端技術を使って薬局現場課題を解決する」ことが得意なチームです。そのために、所属する面々はそれぞれ最先端のAI技術やソフトウェア開発技術に強みを持つ人や、薬局現場のリアルな課題やその裏側の業界背景に精通している人など、様々なスペシャリストが所属しています。
今回のKakeru君開発においても、その知見はふんだんに活用されました。音声の認識性能向上においては、医療ドメイン特有の単語や言い回しに対して、効率的な学習方式を実現することができ、我ながら高い文字起こし性能を達成できています。また、SOAPの執筆においても、様々な流派のSOAPを学習させていき、薬剤師の思考をモデリングすることで、より深みのあるSOAP執筆を達成しています。
3.4. 薬歴AI: Kakeru君を使いこなすコツ
私自身がKakeru君を実際に使用して気づいたのは、「自分が思っている以上に早口で話している」ということでした。
Kakeru君を最大限に活用するためのコツは、以下の2点です。
●「この薬」や「これらの薬」といった曖昧な表現を避け、医薬品名を具体的に話す。
●聞き手に合わせた話す速度を心がける。
つまり「電話の音声だけで服薬指導が伝わる」ような話し方を意識することで、Kakeru君は最高のパフォーマンスを発揮します。これは、患者様への「伝わる指導」にもつながる重要なポイントです。さらに、まだリリースできていない多くの機能を現在も開発陣と協力し企画実装しています。これにより、更にKakeru君はパフォーマンスを発揮する予定です。今後もぜひご期待ください。
4.最後に
「薬歴AI」の本質は薬剤師業務の支援にあります。Kakeru君のような薬歴音声入力AIは、事務作業効率化だけでなく、薬剤師が専門性を発揮できる時間を創出します。私たちmediLabは現場の声に耳を傾け、共に成長するKakeru君を目指しています。AIはあくまで道具であり、それを使いこなすことで患者様とのコミュニケーションや臨床判断により多くの時間を割けるようになるでしょう。薬歴AIの活用はまだ始まったばかり。これからも「薬歴音声入力AI」の可能性を最大限に引き出し、より良い医療サービス提供に貢献できるよう挑戦を続けていきます。皆様の薬局業務における「あったらいいな」を、最先端技術で実現していきましょう。